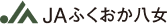日本茶の中でも高級で、上質な旨みと豊かな香りが楽しめる玉露。その特別な美味しさは、一体どのようにして作られているのでしょうか?
今回は、そんな玉露の栽培方法について紹介します。玉露の育て方にはどのような特徴があるのか、その効果や難しさなど詳しく解説するので、玉露の美味しさの秘密を知りたい人は、ぜひ最後までチェックしてくださいね!
玉露とは?

玉露は日本茶の一つで、その中でも最高峰の品質と美味しさを持つといわれています。玉露の産地として有名な地域ではお土産としても人気で、国内外を問わず多くの人に愛飲されています。
玉露の味わいは渋みが少なく、コクのある甘みと旨みをしっかりと感じられます。また、香りもふくよかで、まろやかな口当たりと共に心地よく広がります。水色(すいしょく)は煎茶に比べ深みのある濃い緑色で、湯呑みに注ぐと優しく透き通っています。
これらの優れた特徴を持つ玉露は、栽培に手間と時間がかかることでも知られており、生産量は日本茶全体で見ると決して多くありません。現在、最も生産量が多いのは福岡県の八女で、古くから高品質な玉露の産地として有名です。
こちらの記事では、玉露の特徴についてより詳しく紹介しています。気になる人は、ぜひ合わせてチェックしてくださいね!
玉露の栽培方法「被覆栽培」とは?

玉露生産の難しさは、茶葉の育て方にあります。玉露の茶葉は「被覆栽培」という特殊な方法で栽培され、これには非常に時間と手間がかかるのです。ここでは、そんな被覆栽培の特徴について詳しく紹介します。
被覆栽培の概要と方法
被覆栽培とは、茶葉の新芽が2〜3枚開き始めた頃から茶園全体を遮光資材で覆い、約20日間にわたって日光を遮断して育てる栽培方法です。地域によっては覆下栽培と呼ばれることもあり、被覆方法や使用する資材も様々です。
被覆栽培の方法と特徴は、以下の通りです。
棚がけ被覆
茶園に棚を建て、その上に遮光資材を被せる方法
直がけ被覆
茶株面に直接遮光資材を被せる方法
また、使用資材として最も一般的なのは黒色の寒冷紗ですが、伝統的な「本ず被覆」では、よしずと藁を使用します。本ず被覆を採用している産地は少なくなっていますが、八女地域では現在もこの伝統的なやり方で玉露を育てているところもあります。
被覆栽培の効果
手間と時間のかかる被覆栽培ですが、この茶番の育て方には以下のような効果があるとされています。
- 旨味の増強:茶葉内のアミノ酸(特にテアニン)がカテキンに変化するのを抑制し、旨み成分を保持します。
- 渋みの抑制:カテキンの生成が抑えられるため、渋みが少なくなります。
- 独特の香り:「覆い香」と呼ばれる海苔のような独特の香りが生まれます。
- 葉色の濃緑化:光合成が抑えられることで葉緑素(クロロフィル)が分解されにくく、茶葉の色が濃い緑色になります。
これらの効果を引き出す被覆栽培は、玉露の生産に欠かせない工程です。手間を惜しまず、丁寧に茶葉を育てることで、玉露の特別な美味しさが作られています。
被覆栽培の難しさ
被覆期間の管理は非常に繊細で、遮光率や期間を適切に調整しなければなりません。そのため、玉露の栽培には高度な技術と経験が必要で、実現できる生産者は限られています。特に、山間地での栽培では気温差が大きいため、より細やかな環境管理が求められます。
また、被覆栽培は非常に労働集約的です。50mにも及ぶ長いネットを茶畑の畝一本一本にかけ、摘採前には再びそのネットを回収してから摘採を行う必要があります。これは非常に時間と労力のかかる作業で、生産コストが高くなる要因となっています。
玉露の品質は、被覆栽培の難しさに挑戦し続ける生産者たちによって守られているのです。
被覆栽培の歴史
被覆栽培の起源は古く、室町時代にはすでにその原型が見られたとされています。当初は、茶葉を寒さや暑さから守るという自然な発想から生まれたと考えられています。
玉露そのものの誕生は、1835年(天保6年)に遡ります。江戸日本橋の茶商「山本山」の6代目である山本嘉兵衛(徳翁)が、18歳のときに宇治郷小倉村の茶製造場で実験的に蒸した茶葉をかき混ぜたところ、小さな団子状の茶葉ができました。この茶葉を試飲すると、気品ある風味と鮮麗な色沢を持つ甘露のような味わいだったため、「玉露」と名付けられました。
玉露の誕生後、被覆栽培の技術は徐々に発展していきました。宇治では、茶園全体に葦や藁で覆いをかけ遮光する覆下栽培が始められ、世界に類を見ない「覆下茶園」が登場しました。現在の被覆栽培は、玉露や碾茶(抹茶の原料)の生産に不可欠な技術となっています。
玉露と煎茶は育て方が違う?
玉露と煎茶の製法はほとんど同じですが、茶葉の育て方に大きな違いがあります。玉露は、被覆栽培で日光を遮断して育てるのに対し、煎茶は新芽が出てから茶摘みの時期まで、日光を遮ることなく栽培されます。煎茶の茶葉は十分に日光を浴びて育つため、光合成が盛んに行われ、鮮やかな緑色をしているのが特徴です。
この栽培方法の違いにより、玉露と煎茶は異なる特徴を持つお茶に仕上がります。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。
| 茶種 | 特徴 |
|---|---|
| 玉露 | 甘みとコクのある濃厚な味わいで、渋みが少なく、まろやかな口当たりです。「覆い香」と呼ばれる独特の香りがあります。 |
| 煎茶 | 程よい渋みと爽やかな香りがあり、すっきりとした味わいです。甘みと渋みのバランスが絶妙です。 |
玉露は最高峰の日本茶として知られていますが、煎茶にも玉露とはまた違った魅力があり、価格も比較的リーズナブルなので、日常的に飲まれるお茶として人気があります。
手間も時間もかけて育つ玉露ならではの美味しさ
今回は、玉露の栽培方法について紹介しました。玉露の茶葉は、被覆栽培という特殊な方法で育てられています。資材で茶葉を覆うことで、渋みを抑えながら旨みと甘みを引き出し、「覆い香」という独特な香りが生まれます。
JAふくおか八女では、伝統的な栽培方法とこだわりの製法で作られた、高品質な八女産玉露をお届けしています。味わい深く、まろやかな口当たりが特徴の八女産玉露は、ご家庭用だけでなく贈答用にもぴったりな一品です。気になる人は、ぜひJAふくおか八女の公式サイトをチェックしてくださいね◎